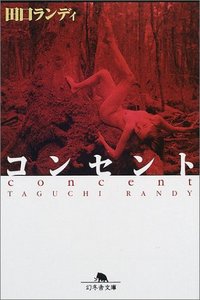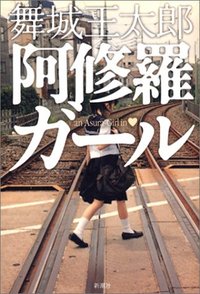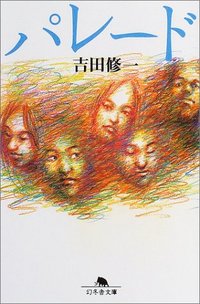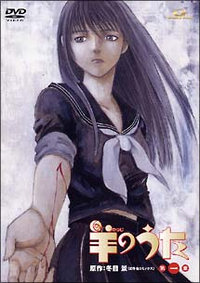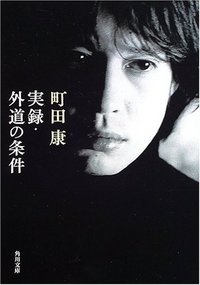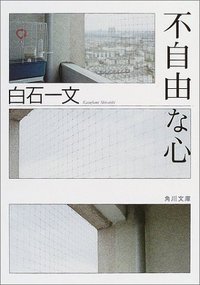すごいエントリーを発見した。
「結婚適齢期の女性が、これから10人の男性と順番にお見合いをして、その中から結婚相手を見つけることにしたとする。相手の意思は無視して良く、「この人と結婚したい」と宣言した時点で結婚できるものと仮定する。ただし、順番に一人づつしか合うことしかできず、今合っている人を「パス」しなければ次の人に合うことが出来ない(「ふたまた」禁止)。また、一度「パス」した人に戻ることも出来ない(「後戻り」禁止)。この条件でその10人のうちの誰かと必ず結婚しなければならないと想定した場合に、最適な戦術を求めよ。」
今後することになるお見合いの回数または恋愛の回数が分かっているとすると、どの程度の相手と出会った時に結婚を決めるのが最も良いか、というのを数学的に証明しようとしているのだ。
つまり、年齢的に「あと○人くらいと付き合えそうだな〜」というのが漠然と分かっているとすると、エントリーにある公式にその人数を当てはめれば、「この人は私的に○○点!」と評価する時、何点以上の評価だとその人と結婚するべき、というのが分かるというもの。
Life is Beautiful 恋の連立方程式
エントリーの最後のように、行動学的にもなんらかの説得力ある結論が出せそうで今後の研究に期待してしまう。
田口ランディ著、「コンセント」を読んだ。
ある日、アパートの一室で腐乱死体となって発見された兄の死臭を嗅いで以来、朝倉ユキは死臭を嗅ぎ分けられるようになった。兄はなぜ引きこもり、生きることをやめたのか。そして自分は狂ってしまったのか。悩んだ末に、ユキはかつての指導教授であるカウンセラーのもとを訪ねるが…。彗星のごとく出現し、各界に衝撃を与えた小説デビュー作。 -「BOOK」データベースより-
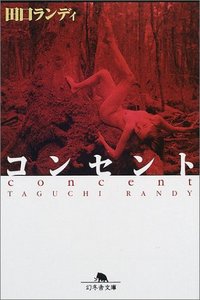
医学生の友人との会話中だったか、どこかの本だったか、病気というのは「普通と違う状態」ということで悪いとは限らないとか、「脈絡なく意味不明なことを言ったりやったりする人を狂っていると言うけど、それはその人の思考経路や脈絡を捉えることができていないだけで、本当はその人にはその人の論理や脈絡がある」という話を聞いたことがある。この小説は、そういう一見精神を病んでいたと思っていた人の謎を解き明かしながら、さらに一歩進んでシャーマニズムというスピリチュアルな世界にまでつっこんだ挑戦的な作品だ。作中に紹介されていたが、
WHOにおける健康の定義によっても「スピリチュアルに健康であること」が明記されているというのは興味深い。
僕は元々オカルト的な話が好きじゃない。超常的なことを信じないというのではなく、僕自身が反証しきれないのでどちらかというと信じているほうだが、相手が反証できないことにつけこみ相手を不安に陥れ、それによって自分が優位に立とうするという心理を、オカルトで生きている人やそれを日常的に人に話す人たちに感じてしまうからだ。あらゆるオカルト話にそう感じるわけではないが、そういう用法が多いと感じている。この小説は、そういった嫌悪感を抱かせない「オカルト」な話だった。この作品でいう超常展開とは、本物のシャーマンの存在と、狂ってしまうということはシャーマンに近づく過程であるということ。実際、精神科医が何年もかけて治療にあたる心の病をシャーマンというか、霊能者というか、そう自称する人々が10分とかで癒してしまう例はいくらでもあるそうだ。元々「疑似科学」自体には非常にロマンを掻き立てられるので、本当は大好きなのかもしれない、オカルト。
また、この作品を受けてのチェインリーディングとして、真木悠介(見田宗介)著「気流の鳴る音」を読むことを自分に課すことにした。
続きを読む...
・「人間の体って、死なないんですよ。・・・人間の体って、固体として変化し続けるんです。ほっておけば、硬直して血が流れ出して、腐って、蛆がわいて、どんどん変化していく。そして、微生物に分解され自然へと還っていく。放置された死体は生きて、変化していくんです・・・」
...元に戻す
舞城王太郎著、「阿修羅ガール」を読んだ。
好きでもないクラスメートの佐野明彦となぜか「やっちゃった」アイコは「自尊心」を傷つけられて、佐野の顔面に蹴りを入れ、ホテルから逃げ出す。翌日、佐野との一件で同級生たちにシメられそうになるアイコだが、逆に相手をボコって、佐野が失踪したことを知らされる。佐野の自宅には切断された指が送られてきたという。アイコは、思いを寄せる金田陽治とともに、佐野の行方を追うが…。
同級生の誘拐事件、幼児3人をバラバラにした「グルグル魔人」、中学生を標的とした暴動「アルマゲドン」。謎の男・桜月淡雪、ハデブラ村に住む少女・シャスティン、グッチ裕三に石原慎太郎。暴力的でグロテスクな事件とキャラクターたちが交錯する中を全力疾走するアイコの物語からは、限りなくピュアなラブ・ストーリーが垣間見えてくる。純文学やミステリーといったジャンルを遥かに飛びこえた、文学そのものの持つパワーと可能性を存分に味わっていただきたい。(中島正敏) -amazon.co.jpのレビューより抜粋-
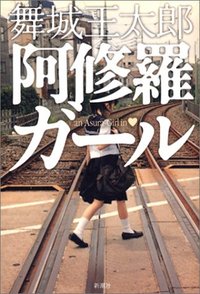
これは凄い。途中まで読み進めて、一旦休憩に本を閉じた時、「これは小説を超えている」と感じた。
ある思想の表現、真実の探求が言語芸術の機能だとしたら、コレは間違いなく高品質の芸術だ。語彙の少ない女子高生の口語調という所謂「純文学」的とは程遠い奇抜な文体を指してこの作品が偉い、ということではく、純粋にアイコの他愛ない思考、幼稚な行動で人間の真実をふんだんに描ききるという技術とセンスとメッセージ、その美学。似たようなものを、綿矢りさの「蹴りたい背中」を読んだ時にも感じたけども、こちらはさらにぶっとんでいる。
そろそろ現れると思っていた、「2ch」を代表とするネット上の匿名集合体社会の、そのリアル社会とそこに生きる個々人への影響力をしっかり取り上げた作品だということも特筆に値する。
文学の力を味わうには今ある最先端の作品の一つだろうということで、超お勧めします。
以下、印象深いパッセージをいくつか。
続きを読む...
・減るもんじゃねーだろとか言われたのでとりあえずやってみたらちゃんと減った。私の自尊心。
・自分を犯した変態の股間を銃で打ち抜いてからその人はブルース・ウィリスに「アーユーOK?」とか訊かれて「アイムプリティファッキンファーフロムOK」って答える。アイムプリティファッキンファーフロムOK。変なボール口の中に入れられて無理矢理変態にお尻を犯されたらそれはやっぱりそうだろう。アイムプリティファッキンファーフロムOK。「OK」なんかからは程遠いんだろう。あの黒人の人はホントに可哀想だ。
でも私は?
私はOK?
うーん。
うん、OK。
少なくともまだ、私はアイムプリティファッキンファーフロムOKって感じではない。
私はとりあえず顔射も口の中でドピュドピュゴクンも中出しもプリズンエンジェルも避けられたのだ。
うん、OK。
これまでの人生の中で一番最高の時って訳じゃないし正直辛いけど、でも大丈夫。私はまだまだやってける。
・正直な物言いだね陽治。なかなか人が言わないことだけど、ホントのこと。人の親切心にも同情心にも、その人なりの限界・境界があるってこと。誰かが物凄い苦痛を感じてのた打ち回っていても、それが遠い場所の出来事だったり現実感薄い感じだったりした、人はちょっと手を差し伸べたり、一歩歩いたり、チラッと見ることすら億劫で、しないということ。
-中略-
私にも陽治にも他のほとんどの人にも、ヒーロー以外の人間には、現実的な人生、生活、ライフってもんがあるんだ。そういうもの背負ってる人間においては、やっぱり同情心と面倒臭いが綱引きやることになるんだ。「かわいそー」と「だる〜」がいつも戦ってるんだ。それで普通なんだ。
陽治はこのままでいい。このままでいい。
でも陽治にもヒーローになって欲しい。陽治の同情心はちゃんと面倒臭いに勝って欲しい。陽治の貴重な「かわいそー」がだらしないつまらない「だる〜」なんかに負けて欲しくない。陽治がエチオピアやら月の裏やら別の時空に走って行くなら私はすっごく丸ごと全力で応援するし、永遠にいかなる場合でも陽治を肯定し、愛し続けるのに。
いやいや私は今のままの陽治で十分愛して肯定して応援するから。
う〜。
・私はカンちゃんが電話の向こうで泣いてングング喉を鳴らしてクヒーンとか言ってスガスガ鼻を鳴らしてるのを聞きながらなんか冷める。まあでも私も一緒だ。私もカンちゃんと同じでわがままだから、私にはカンちゃんを責める資格なんてないし別に嫌な風に思わない。私も陽治の気を引くためにいろんなことするし、カンちゃんも《いろんなことにおいて正しいことをやるんだしやりたいんだし何かで間違えたらそれを自ら認めてすぐに正していくっていう自分》って自己像を守るためには何でもやるんだ。そんでいいし、そんで普通。頑張れカンちゃん。
...元に戻す
吉田修一著、「パレード」を読んだ。
都内の2LDKマンションに暮らは男女四人の若者達。「上辺だけの付き合い?私にはそれくらいが丁度いい」。それぞれが不安や焦燥感を抱えながらも、“本当の自分”を装うことで優しく怠惰に続く共同生活。そこに男娼をするサトルが加わり、徐々に小さな波紋が広がり始め…。発売直後から各紙誌の絶賛を浴びた、第15回山本周五郎賞受賞作。-「BOOK」データベースより-
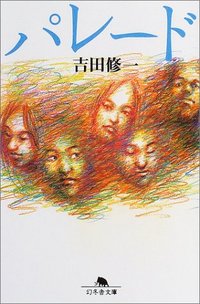 以前読んだ「パークライフ」が良かったので
以前読んだ「パークライフ」が良かったので、彼の別の作品を手に取ってみた。彼の文体は何故か僕にとってとっても読みやすい。文章を読む、ということはそれなりに能動的な行動なので、作品によってはかなり疲れたりするし、そうでなくとも一定の体力というか、脳力というか、とにかく労力を要する。けど、彼の作品はほぼノーストレスで、スっと入ってくる。このパレードも、導入はごく普通の大学生の日常をリアルに描いていて、その親近感からかやはり非常に読みやすい。物語は章を追うごとに、5人暮らしする男女5人のそれぞれへ視点が移っていく。視点は移るが、時間軸が一つまっすぐに続いているので、前章の続きを別の人物の視点で語っていく、という構成。そして、そうやって5人全員の主観が語られていくなかで、その人間関係の微妙さと、絶妙な距離感を浮き彫りにしていくのが実に巧い。5人はそれぞれどこか病んでいるんだけども、本人達はそれに気付かない、というかその苦悩を無視するかのようでいる。描写は極めてリアルであるけども、登場人物はどこか異常で、一見非日常的。でも、現実の人間達も、こうやって苦悩や病理と折り合って生きているのかもしれないと思えてくる、そういうリアルさがこの小説にはある。読んでいる途中は、なかなかにほのぼのとした感覚で読んでいたけども、読了後に残るのは、当初は予想もし得なかったある種の不快感と、恐ろしさ。全く良く出来た小説だと思った。
最近漫画を読む機会もめっきり減ったので、これからは良作に出会ったら漫画もBiblio Logに記録して行こうと思う。
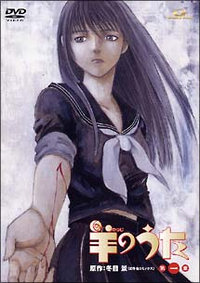 冬目景の「羊のうた」を読んだ。父親の友人夫婦に育てられたこと以外は、ごく普通に暮らしてきた高校生の一砂。ある日突然の吸血衝動に襲われ、密かに想いを寄せていた同級生の八重樫を襲いかけてしまう。自らの衝動に戦きながら吸血衝動と共に蘇った記憶を頼りに生家に赴くと、そこには幼い頃に別れた姉、千砂の姿があった。千砂は、二人が吸血鬼のように血を欲する奇病を生まれ持つ家系の出であること、もう普通の生活は送れないことを告げ、一砂に自分の血を差し出した・・・ ・・・という風に始まるお話。
冬目景の「羊のうた」を読んだ。父親の友人夫婦に育てられたこと以外は、ごく普通に暮らしてきた高校生の一砂。ある日突然の吸血衝動に襲われ、密かに想いを寄せていた同級生の八重樫を襲いかけてしまう。自らの衝動に戦きながら吸血衝動と共に蘇った記憶を頼りに生家に赴くと、そこには幼い頃に別れた姉、千砂の姿があった。千砂は、二人が吸血鬼のように血を欲する奇病を生まれ持つ家系の出であること、もう普通の生活は送れないことを告げ、一砂に自分の血を差し出した・・・ ・・・という風に始まるお話。
吸血衝動、和服、日本家屋、近親相姦、血の繋がらない家族。暗くて救いの無い話なんだけども、読み終わった後に何か心に残る作品だった。長さも7巻と丁度良く、一つの物語としてよいまとまりを持っている。そして何より絵がとても綺麗だ。物語が進むに連れて深まっていく悲壮感と共に、絵柄も益々綺麗になっていく。悲しいのに、見とれてしまう。
この作品、アニメ化も実写版映画化もされているようだ。でもなんかこの漫画の世界の雰囲気は超えられない気がする。久々の良作。冬目氏の漫画は初めて読んだけども、他も期待大だ。
特に新しいわけではないけど便利なサイトを発見したのでご紹介。
「meebo」
 ブラウザ上で、MSNメッセやAIM、Google Talkなんかにログオンできちゃうサイト。偉いのは、PCにMSNメッセンジャーとかがインストールされてなくても使えるところで、仕事先や旅先のネットカフェやひとんちのパソコンで突然メッセにログオンしたくなったときにいつでも使える。日本語も問題なく送信できた。
ブラウザ上で、MSNメッセやAIM、Google Talkなんかにログオンできちゃうサイト。偉いのは、PCにMSNメッセンジャーとかがインストールされてなくても使えるところで、仕事先や旅先のネットカフェやひとんちのパソコンで突然メッセにログオンしたくなったときにいつでも使える。日本語も問題なく送信できた。
見たところファイル転送機能はついていないようなので、ファイル転送を制限されるようなオフィス環境でも使用することができるはず。
続きを読む...
と、はしゃいでたら、もともと「WEB MESSENGER」って機能が実装されてたんですね・・・知らなかった。(友人に指摘される。恥)
ということで利点はいろんなクライアント(特にGoogle Talk)が軽いインターフェースで使える、ということでしょうか・・・
...元に戻す
町田康著、「実録・外道の条件」を読んだ。
許さん。復讐の鬼と化した俺は三年間洞窟にこもって本稿を書き綴った・・。
約束の場所に行ってもおらず、携帯に電話してもつながらない記者。撮影現場で目もあわせず、紹介されても挨拶もろくにできないヘア&メイク。などなど以下延々と続く。鞭無能な各種マスコミ、業界人へ怒りの町田節!-amazon.co.jpから引用-
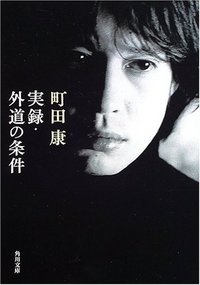
町田康の文学が読みたくて古本屋の本棚を漁っていて手に取ったのがこの作品。小説だと思って買ったら、エッセイ集のようなものだった。彼の業界にて体験した理不尽な出来事の数々を面白おかしく愚痴りながらそれをもたらした人々を達観した視点から鋭く批判する。上に引用した紹介文を買う前に読んでいたならおそらく買っていなかったな。けど、裏表紙にあった本文からの引用を使った紹介文、「なにゆえかくも話が通じないのであろうか。丁重な文面であるにもかかわらず、その文面のなかにときおり顔をのぞかせる強い調子、攻撃的な排他性のごときを改めて強く感じ、その根拠として彼らが標榜しているボランティアという概念について、普段そんなことについてまるで考えたことのなかった私が、この困惑を契機に深く考えるようになってしまったというのは、いったいいかなる因果・因縁であろうか。(「地獄のボランティア」より)芥川賞受賞第一作となった傑作小説集。」を読んで、これは世の中の欺瞞について町田流に語ってくれるのかな、と思ったわけだから、その点は裏切られなかった。
読み進んでいくと、文章は頭の回転が早い人にありがちな無駄に長い文章(読点を多用していろんな事実を一つの文章で一気に語ってしまう)で、読みにくいことこの上ないのだがあまりの語り口の滑稽さに笑えてきて、気付くとこの町田康という人物を好きになっているから不思議だ。最後の一編はくどさが過ぎて読むのが辛かったけど。
次は是非彼の渾身の長編小説を読んでみたい。
白石一文著、「不自由な心」を読んだ。
大手企業の総務部に勤務する江川一郎は、妹からある日、夫が同僚の女性と不倫を続け、滅多に家に帰らなかったことを告げられる。その夫とは、江川が紹介した同じ会社の後輩社員だった。怒りに捉えられた江川だったが、彼自身もかつては結婚後に複数の女性と関係を持ち、そのひとつが原因で妻は今も大きな障害を背負い続けていた…。(「不自由な心」)人は何のために人を愛するのか?その愛とは?幸福とは?死とは何なのか?透徹した視線で人間存在の根源を凝視め、緊密な文体を駆使してリアルかつ独自の物語世界を構築した、話題の著者のデビュー第二作、会心の作品集。-「BOOK」データベースより-
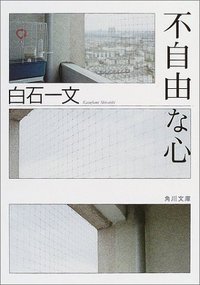
読んで楽しい小説ではなかった。生々しい話であるからというのもあるだろうけど、著者が読者のためにこの作品を書いていないからかもしれない。5つの作品を収録してあるのだけど、どれもその辺のどこにでもいそうな、ちょっと仕事ができて人並みに女性付き合いのある、ごく普通のサラリーマン達が主人公。彼らの仕事内容等に関する設定も細かくて、会社人というのはこういうものかと思わせるリアルさがある。そして、リアルがゆえに、重苦しい。冷めた夫婦愛、親子愛、不倫、社内の派閥、親の看護、死、転属、リストラ、etc。30代や40代の日本人男性は、みんなこんなにも鬱屈したものを抱えて生きているのかな、と。だけど、やはりその日本人サラリーマンの誰もが思うであろう、その時続けている生活の是非、自分の人生の意味への問いかけ、人間の心の本当の裡、そんなものを真面目に真面目に描いている。女性には不愉快に思える内容かも知れないけど(男の身勝手さが男の言い分でこれでもかというほど描いてある)、それだけに、今の日本の中年の男女関係を考えるにあたって読んでよかったと思った。特に表題作のインパクトは大きかった。特に、死に対する考察。人間は最も愛する人の死によって、死の恐怖と生への執着から解放される、というもの。したがって、愛する人への最も尊い行動は、その愛する人の腕の中で死んであげることだと。主人公がこの考えに至るまで色々あって、簡単に共感はできないのだけども、深く、考えさせてくれた。
読むなら、表題作だけじゃなくて、初めから通して読んだほうがいいと思うけど、途中で辛くなるかも知れないのであまりお勧めはしない。
なぜか姉貴からマンガバトンが来た。僕が読んできたマンガの殆どは姉貴の本棚のマンガだというのになにを今更・・・という気がしないでもないけど、あえて真面目に答えてみる。
1. Total volume of comic on my Bookshelf(本棚に入ってる漫画 単行本の冊数)
今はゼロ。学生時代は9冊。最終兵器彼女とスワロウテイル。スワロウテイルは誰かに借りていた気がする。うちの家庭では、普段はマンガを揃えるのは姉貴だったんだけど、最終兵器彼女、これ、何気に自分で自分のために買った唯一のマンガ。なのに、買った直後姉貴の家遊びに行ったら姉貴も揃えてた。
姉貴が揃えた、実家にあるマンガも入れると、500冊くらい、と姉貴が言っている。(もっとあるような気がするんだけど・・)
2. Comic thought to be interesting now(今一番面白い漫画 )
20世紀少年、ジパング、ベルセルク!
ベルセルクは今と言わずずっと面白い。高校の時に、voriに「日本で最高のマンガ」と勧められて読んで、以来そのとおりだと思っている。20世紀少年はこれまでこれを手にとってこなかったことが損としか思えないほどの傑作。作者の構成力が凄すぎる。ジパングも比較的最近始まった連載だけども、今後を一番期待しているのはこれ。戦国自衛隊の近代版だけど、そこからのストーリーの展開が上手すぎる。深いテーマも抱えていて、一冊読むごとにため息が出る、完結すれば傑作中の傑作となるでしょう。
3. The last comic I bought (最後に買った漫画 )
最終兵器彼女7巻。賭けに勝って買ってもらったものを入れると、修羅の刻10巻。
4. Five comic I read to a lot, or that mean a lot to me (よく読む、または特別な思い入れのある5つの漫画 )
1.ドラゴンボール(鳥山明)
小学1年の頃、親と本屋に行って、普段モノをあまりねだった記憶はないんだけど、この時どうしてもマンガを一冊買って欲しくて、なぜかドラゴンボール13巻をおもむろに手にとって買ってもらった(悟空対初代ピッコロ大魔王が戦う場面)。そのちょっと後、道端に落ちていたジャンプを拾って、ドラゴンボールのページをめくってみたら、なぜかみんな揃ってやられてて悟空とピッコロとクリリンが一緒になってなんかでかいヒゲと戦っているという異様なシーンをやっていた(ホントは息子の悟飯達がナッパと戦っているシーンだったことが後に分かる)。これがマンガ版ドラゴンボールとの出会い。(アニメはもっと前から見ていた)通学路を歩いている間元気玉が出ないかエネルギーをためてみた、とかは誰でもやったことあるよね。高校を卒業してから、一部の友達と「ドラゴンボールクイズ」なる遊びに熱中したり。僕と同年代の男の子はみんなフリーザ第一形態の戦闘力やポルンガを呼び出すナメック語の呪文とかは常識として知っているものだと思っていたんだけど、どうやらそうでもなかったみたいってことを最近になって知る。
思い入れありすぎて文章が長くなりすぎた(笑
2.がんばれ元気(小山ゆう)
我が家に最初からあった作品。親父が以前から揃えていたマンガで、物心ついたらすでに本棚にあった。姉貴が自分でマンガを買ったりするようになるまでは、うちにあるマンガといえばこれとかオバQで、何度全部読み通したか知れない。今思えばボクシングで必殺技なんてありえないが、渋い人間ドラマで、試合以外のシーンも印象的なものばかり。話も今のマンガのようにだらだらと続かず綺麗にまとまっているし、きっと今読んでも本当に面白い、名作だと思います。
3.修羅の門、修羅の刻(川原正敏)
僕にとって格闘マンガの決定版。陸奥圓明流は実在するんです!!修羅の門は、ただただその熱さに涙がこみ上げてきてしまう。主人公根暗なのに。無空波とか四門が出たらまず泣く。修羅の刻も涙なくしては読めない、感動の大作シリーズ。あれで大河ドラマつくって欲しいよ。(歴史ファンから猛反発受けることを必至だけど笑) みんなも布団を干すときは虎砲の練習をしよう。
4.俺たちのフィールド(村枝賢一)
サッカーやらない作者が書いたサッカーマンガ。笑いあり涙あり熱血あり、だけど少年漫画にしては妙にすっきりというかなんというか、とにかくそれまで読んだ少年マンガとはちょっと違うと思ってたんです。名台詞満載、これも泣きまくりの感動作だったなぁ。あと、サッカーマンガとしてリアルかどうかは僕には分からないけど、これ読んでサッカー観戦が面白くなったのは確かです。
5.D−ASH(作:北沢未也+画:秋重学)
全5巻と短いけど本当にイイ。珍しい陸上マンガです(ホントに珍しいかは分からないけど、僕はほかに小山ゆうの「スプリンター」しか知らないや)。12年生の頃、ケンユーの部屋で読んで、かなり感動した。ウェブ検索でもあまりひっかからない、アマゾンに在庫もない、かなりマイナー作のようだけど、僕の中ではかなりの名作です。「マンガ」を書くのが本当に上手い人で、マンガならではの躍動感や心の動きの演出が素晴らしい。小学校の頃に読んだ少女漫画、「この手をはなさない(小花美穂)」以来、こういう子供の頃の初恋の人と大人になって再会系の話に弱いんだよな・・・
次点として、3x3eyes、ジョジョの奇妙な冒険、北斗の拳、富樫作品s、カイジ、ダイの大冒険、ドラクエ4コママンガ、Clamp作品s、ここはグリーンウッド、巨人の星、ゴッドサイダー、、、、きりがないですね・・読んだマンガにはどれも思い入れあります。
5. Five people to whom I'm passing the baton (バトン を渡す5名)
バトンとかやりそうにないけど・・・
・kosukeyaz
・shunrin
まぁスルー可です。