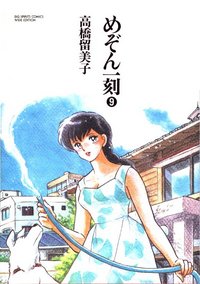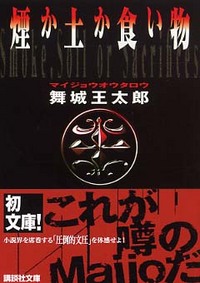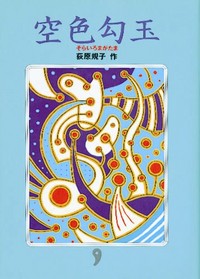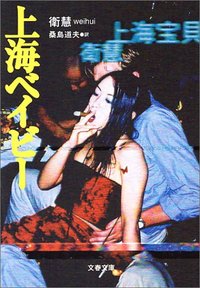July 23, 2006
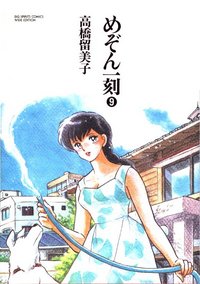
高橋留美子作、「めぞん一刻」を読破した。いわずと知れた80年代ラブコメ漫画の金字塔。小さい頃にアニメで少し見ていたけど、その頃は対して面白いと思えず続けて見てなかった。
高橋留美子作品は、小学生の頃連載してたらんま1/2が開始当初は好きだったけども、途中でだれてぐだぐだな展開になり始めてから興味を失い、以来現在の犬夜叉までその流れは続いていそうで良いイメージがない。でもやっぱりめぞん一刻は良い、と頻繁に聞くので通して読みたいと思っていた。
読んでみたら面白いこと面白いこと。優柔不断でだらしなくて意気地のない五代君と、頑固ではやとちりで妬き餅焼きで五代君以上に優柔不断な音無響子さん。こんなに主人公を応援したくなるのも珍しければ、こんなにヒロインにイライラさせられることも珍しいくらい感情移入した。いや、響子さんサイコーなんだけども。五代君があまりのも情けないのがいけないんだけども。しかしなんでこんな主人公に肩入れできるのかが未だに自分でも理解できない。
面白いのが、作中のほとんどのすれ違いが、今の世のように携帯電話やメールが普及していたら起こらない類のものだったということ。共用の置き電話の会話を響子さんが盗み聞きして誤解する、というエピソードが腐るほどあった。あと面白かったのは物語がどうやら連載とリアルタイムで進行していたということか。7年連載したらしいけど、途中響子さんの亡き夫の命日がたしかに5回も6回も出てきた。季節ネタも沢山あったし。五代君18歳、響子さん21歳から物語は始まり、最後は就職浪人した五代君が無事就職し、響子さんは27,8歳になっていた。それに思い至るとラストはやはり感慨深かったなぁ。
有名なプロポーズのシーンはラストではなかったと知って意外。あの後に2話エピローグがありました。そっちのほうが感動的だったな。五代君の最後の墓参りには泣けた。一番意外だったのは、終盤ベッドシーンなどがしっかりあったとこ。らんまや犬夜叉のイメージでてっきり少年誌(サンデー)連載かと思っていたら、ビッグコミックス連載だったんだね。というよりあの長さの連載でそれまで全くその手の話題に触れてこなかったのにいきなりだったってことに驚いたのだけども。でも一人の青年の青春全てをかけた恋愛を描ききったのがやっぱ一番エライ。
いやー名作。
July 22, 2006
今日親父が定年を迎えた!定年ってことは、60歳なわけで、60歳ってことは還暦なわけで、還暦ってことは暦が巡ったわけだから当然年男なわけで、ついでに言うと誕生日なわけで。すごい、めでたい。
勤続36年。自分は庭いじりが好きな温厚な父の姿以外ほとんど知らないけど、父の送別会ラッシュの話を母から聞いているとなんだか会社でも凄く人望の厚い人だったようで驚く。A1サイズの寄せ書きをもらったり、高級ワイン入りワインセラーをプレゼントされたり、翌月まで送別会の予定がつまってたり。別に意外とは思わないけど、実際に自分の父が人から慕われているというのが、なんだかそうであったらいいなという願望が、現実であった(らしい)という意味で。
物心ついた時にはすでに父親の勤め先=凄いところだと思っていた。いつも本当に誇らしげに話すから。誰もが知ってる世界のエンジンメーカー。幼稚園の頃から同じ会社に勤める父を持つ友達と、その会社に入るだの入らないだのという話をしていたんだから今考えると笑える。世の中にそこ以外の会社があるということすら分かっていなかっただろうに。でもその頃から今に至るまで、実際にその会社はとってもカッコいいと思ってるし、今でも何かと気になる会社だ。製品も業績も創業者から受け継がれてるというスピリットも。テレビCMがいつもいけてないのが玉に瑕なんだが。
親父は中学の頃にはもうその会社に就職することを夢見ていて、そのためにその会社へ就職した人が一番多かったという理由で大学を選び、一度就職試験で落ちて、親に頭を下げて自主留年し、翌年の試験でリベンジして入社を果たしたそうだ。
こんな話を子供の頃から聞かされていたからか、会社とはこういう思いで入るものだと、実際に自分が就職活動をするような歳になるまで何の疑いもなく思っていた。入りたい会社に入る、目指したい道を目指す。僕が起業という道を選択したことに、この父の就活エピソードは深く影響している。だって、こんな風に入りたいと思う会社なんてなかったから、自分のやりたいことをやってみようと思うことに抵抗は無かった。
父は庭いじりがかなり好きだ。今実家の庭には、キュウリ、トマト、ニラ等の野菜の他に、レモン、梨、さくらんぼ、ビワ、ブドウ、ザクロ、カリンなどの果物が生る。小さいけど結構楽しい庭。しばらくは、庭や熱帯魚やオーディオと言った趣味と、孫との触れ合いをのんびり楽しみながら悠々自適な生活を送るみたい。今までほとんど休みなく働いて来てくれたおかげで、僕はこうやって好きなことを目指すっていう贅沢な道を選ぶことができてるのでゆっくり休んでくれと言いたいところだけど、とりあえず実家に帰るたびに草むしり手伝わされてたらかなわないので、さっさと次の仕事見つけろと言うだけ言っておこうと思う。
July 17, 2006
July 09, 2006
舞城王太郎著、「煙か土か食い物」を読んだ。
腕利きの救命外科医・奈津川四郎が故郷・福井の地に降り立った瞬間、血と暴力の神話が渦巻く凄絶な血族物語が幕を開ける。前人未到のミステリーノワールを圧倒的文圧で描ききった新世紀初のメフィスト賞/第19回受賞作。-「BOOK」データベースより
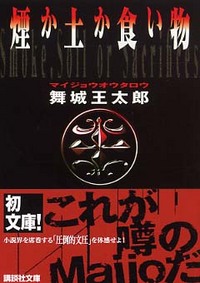
舞城小説三冊目。
阿修羅ガール(2003/01)→
世界は密室でできている(2002/04)→煙か土か食い物(2001/01)、と発表順で言ってだんだんと遡って読んでいるわけだけど、彼は最初からぶっとんでいた。今回のがデビュー作。色々と凝った試みを見せていた阿修羅ガールに比べると、この作品はエンターテイメントど真ん中という感じで、一ページ目からラストまで落ち着くことなく一気に読者を引っ張っていく。読書はおっくうとか、面白い部分に達するまでに飽きてしまう、という人でもこの人の作品ならどんどん読めるんじゃないだろうか。
この作品、書店等のジャンルではミステリーと位置づけらるんだろうけど、実際はミステリー風の全く異質なものだ。途中で犯人が誰とかどうでもよくなってくる。誰かがアマゾンのカスタマーレビューでうまいことを書いていた。
"ゴッド・ファーザー"がマフィア映画というジャンルでくくられがちだがその辺は単なる舞台設定に過ぎなくて実は「家族」の物語だったんだ…と実際に見ればすぐ分かるように、これも読み始めてすぐ、「あっこれもしかしてミステリじゃありませんね?」と気付く。
記事最上部に引用した紹介文にもあるように、多分に暴力と狂気がフィーチャーされた物語だけども、ミステリーの基礎である殺人事件の謎と過剰なまでの暴力をとりはらったら、残るのは家族の物語。そしてその極めて凄惨でアンリアルな家族模様を取り払ったら、残るのはとっても真面目でまっすぐな、そして極めてリアルな愛情の物語のはずだ。こんなに狂った話で、最後にうるっとさせられるとは思わなかった。これは、「世界は密室でできている」でもやられたパターンだ。この人の描くキャラクターの温かさになぜか胸を打たれる。
この本を読むには、まずこの人の乱暴な口語調の文体を受け入れられなくては辛いと思う。句読点も改行も少ないし、なによりそもそも著者がこの作品を書き上げる動機となっていそうなほどに、これまでの小説上のルールを破りまくっている。謎を推理するのではなく、謎が現れた瞬間即座に脈絡なくひらめく、とか、第一人称なのに現在進行形で書かれたりする、とか。正統的な小説に読みなれている人には読みづらいことこの上ないでしょう。でもそれを受け入れられたら、きっと好きになってもらえそうな気がします。
ところで、この舞城王太郎を世に出した、「メフィスト賞」ってのがどんな賞なのか気になったので調べてみた。すると、結構有名な作品がちらほら。未読だけど、森博嗣の「すべてがFになる」、殊能将之の「ハサミ男」なんてのはよく名作として耳にする。西尾維新もメフィスト賞出身だったとは驚き。最近少々首を突っ込んでみたライトノベルの世界で、時代のエース的扱いをよく受けてる人だ。受賞作の「クビキリサイクル」もこの前友達が読んでたな。でも他の歴代の受賞作とその簡単なレビューなんかを見てみたけど、なんか、結構微妙だ。あたりはずれが激しそうな印象。選考を、ファウストっていう小説雑誌の編集部内だけで行ってるらしい。「独断と偏見で」というやつ。でも、その独断と偏見の変な基準から、この才能を見出した。今では、ライトノベルというジャンルも、ミステリーというジャンルも超えて、芥川賞候補に挙がり、三島由紀夫賞に輝き、今度は小説家という枠を越えてマンガや映画製作に乗り出している。ジャンルとかほんとどうでもいいと思わせてくれる。こんな変な人を出すんだから、きっとすてた賞じゃないんだろう。そのうち他の受賞作にも手を出してみよう。
荻原規子著、「空色勾玉」を読んだ。
国家統一を計る輝の大御神とそれに抵抗する闇の一族との戦いが繰り広げられている古代日本の「豊葦原」。ある日突然自分が闇の一族の巫女「水の乙女」であることを告げられた村娘の狭也は、あこがれの輝の宮へ救いを求める。しかしそこで出会ったのは、閉じ込められて夢を見ていた輝の大御神の末子、稚羽矢。「水の乙女」と「風の若子」稚羽矢の出会いで変わる豊葦原の運命は。
福武書店版の帯の文句がなによりもこの本の世界を物語る。
「ひとりは「闇」の血筋に生まれ、輝く不死の「光」にこがれた。 ひとりは「光」の宮の奥、縛められて「闇」を夢見た。」
不老不死、輪廻転生という日本の死生観や東洋思想とファンタジーの融合をなしえた注目の作品。主人公2人の成長の物語としても、その運命の恋を描いた恋愛小説としても、一度表紙を開いたからには最後まで一気に読ませる力にみちている。中学生以上を対象とした児童書ではあるものの、ファンタジー好きの大人の読書にも耐えうる上質のファンタジーである。-amazon.co.jpの商品説明より
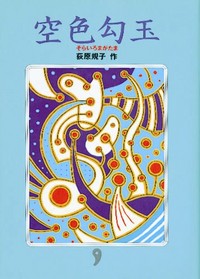
最近ファンタジーがマイブームです。良質のファンタジーを求めてる時に友人に紹介してもらったのがこの作家。ファンタジーといえばやはり「剣と魔法」の世界観で、当初はやはりそういうものをイメージしていたのだが、こういう日本の古代とか、剣とか勾玉とかってキーワードに元から弱いので食いついてみた。
世界観は大胆にも日本の神話時代。古事記とかに出てくるような時代。登場人物は名前こそ違うものの、明らかにアマテラス、ツクヨミ、スサノオの三貴士がモデルだ。日本風のファンタジーときたら、陰陽師系やもののけ姫のような八百万の神々と言ったモチーフなら触れたことがあったけど、この三神をキャラクターとして動き回らせるような物語には触れたことがなかった(スサノオはわりとお話しになりやすい伝説が残ってるので別だが)。それだけに凄く新鮮で、心躍らされた。日本神話には特別な思い入れがあるのです。
物語は会話中心でさくさくと進み、読み手をぐいぐいと引き込む。盛り上げどころの描写が少々物足りないと思わないでもないけど、クライマックスの迫力は申し分なかった。そこでそれを出しちゃうのか、と。
登場人物は、輝の大御神(イザナギがモデルと思われる)を崇める光の軍勢=神の軍団と、闇の大御神(同じくイザナミ)に守られる闇の軍勢=人間の勢力とに別れて戦う。面白いのが、ヒロインは闇の側につき、闇=人間として、神に歯向かおうという、光対闇の対立で読者の共感を闇に置こうとしているところ。イザナミは古事記でも黄泉の国の支配者とされ、闇はそのまま死を指し、この物語はしいては死の肯定、限りある時間の肯定、そして有限の時間の中でこそ人間は情を知る、という生の肯定を根底のテーマとして据えているように読める。児童文学らしい、読後に前向きな気持ちにさせてくれる一冊だ。
3部作らしいけど、とりあえずこの話はこの一冊で完結しているので、今は他の作品にどんどん触れていこうと思います。
衛慧(Wei Hui)著、「上海ベイビー」(原題:上海宝貝」)を読んだ。中国では発禁処分になると有名になるとかで、この作品もおそらくそれが知名度を上げた原動力だったんだろうけど、中国人の知り合いも大抵は知っている有名な作品のようだ。
クールな新人作家、衛慧が発表した本書は中国本土ですでに大ブレイク中の小説。不機嫌で短気で驚くほどみだらな筆致により、セックスにおぼれながら愛を模索する1人の美しい女流作家を描いた新感覚の作品で、大胆な性描写のため中国政府から発禁処分を受けたいわくつきの話題作だ。そのきわどさはヘンリー・ミラーの『Tropic of Cancer』(邦題『北回帰線』)に引けをとらず、衝撃度は『Trainspotting』(邦題『トレインスポッティング』)に負けていない。「魔都」上海の先端風俗の中、どんどん過激な情事にはまっていく主人公が飛びはね、わめき、手加減なしに全力疾走する姿を描いた本書は、アジアにおける新世代の台頭を表現した作品でもある。-amazon.co.jpの商品説明より抜粋
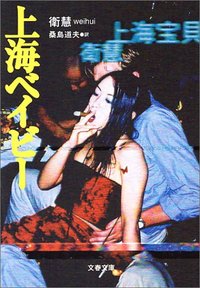
この紹介文はちょっと閉口ものだけど、読んでみると意外に引き込まれる。ストーリーはほぼ無いに等しい、「過剰に自己投影されている」とされる著者の創作にあたる苦悩を描いた私小説的内容で、面白いことは無いはずなんだけど、とにかく文章がかなり新鮮。日本人にはまず思いつけないだろう表現がいたるところにあって、こんな表現があるんだと感心しっぱなしだった。本当に綺麗な描写が盛りだくさんで、たまに狙いすぎな表現が鼻につくけど(特にラスト)、全体的にかなり文章を味わう感性を刺激される。外国語作品の日本語訳なのに、日本語の可能性を広げられた気分だった。(今ちょっと本が手元にないので引用できないのが残念)
主人公は自己愛の強いかなり不安定な人物で、共感するのは男の僕にはかなり難しいんだけども、これは性差コンシャスな女性に物凄く受けそうな気がする。友人の何人かにはかなり強くお勧めしたい。スタイリッシュな文体もうけそうだ。享楽主義な人にもそれを軽蔑する人にもお勧めだと思います。
July 02, 2006
「豪一郎がゆく:鏡の法則(ハンカチを用意して読め!)」より
友達に教えてもらいました、鏡の法則。
人生の大切な考え方が実話に基づいて物語で書かれているのですが、読んだ人の90%が涙するそうです。(誰が計ったんだろう?でもぼくも涙が噴き出しました)
ぼくはこれを読んで、人間として大切なことを再認識させられました。読むのに10分ほどかかりますが、その時間を投資する価値は大いにあります。
これはホントにハンカチ必要でした。名著「七つの習慣」でも似たようなエピソードがありました。ちょっと長いけど読んでみて欲しい。こういう視点で世の中と向き合えるような人間に早くなりたい。
他にもためになるエントリーがあるんだろうかとサイトを見回してみると、管理者の写真と名前があることに気づく。・・・新井豪一郎さん・・・
・・・
友達(現TBSアナウンサー新井麻希)の兄ちゃんだ!空手部の先輩だ!すげー。
このサイト、はてなブックマークで大量にリンクされてたんで発見したんですが、こういうのに知り合いのブログが出て来るとは。先輩、お元気でいらっしゃるのでしょうか・・・お子さんも凄く可愛く成長されてるようで何よりです。とてもためになりそうなブログなので今後もたまに覗かせて頂きます。
ついでに麻希の公式プロフィールを久々に覗く。好きな音楽、RASPUTINって・・・(高校同期が当時から今でもやってるパンクバンド)
なんかネットの海も広大なようで案外狭く感じてしまう一瞬でした。